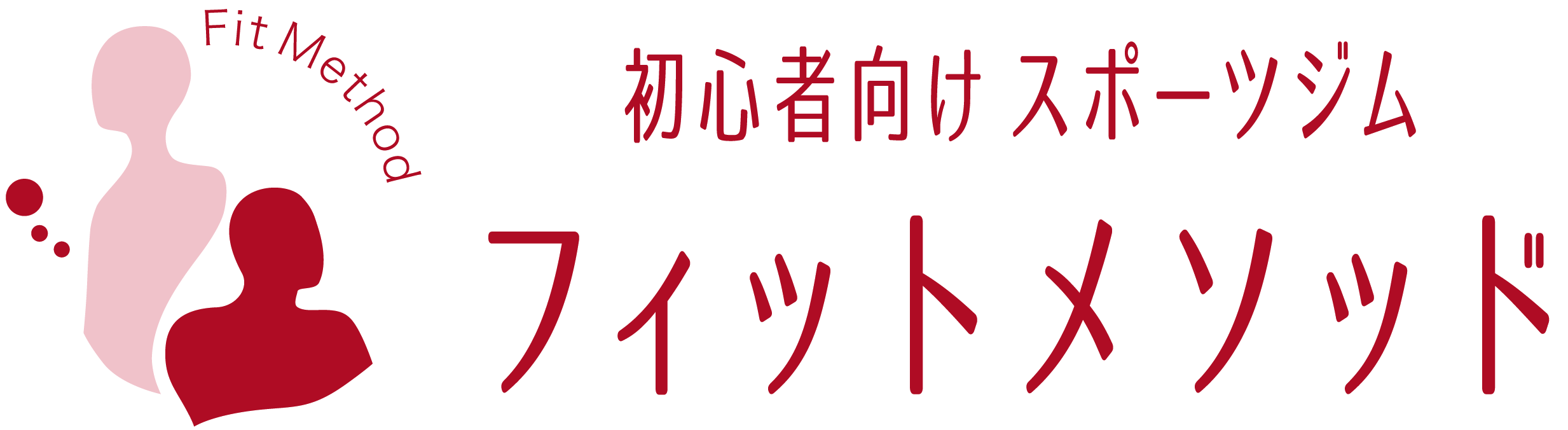札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。
今回は「持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングは低負荷ではなく高負荷がオススメ ②」というタイトルで記事を書いていきます。
前編 の続きです。
低重量・高回数ではなく「高重量・低回数」のトレーニングをオススメする理由
持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングでは、一般的に低重量・高回数でのプログラムが多く用いられる印象を受けますが、筋持久力の改善に加え筋肉量 = 体重の増加が起こると判断され、むしろパフォーマンスに悪影響が及ぶリスクが考えられるとお伝えしました。
筋持久力が持久系スポーツにおいて重要になるのは明白な一方、筋肉量(体重)の増加は懸念材料として知られており、低重量・高回数のトレーニングによって筋持久力の改善というメリットを享受したとしても、それは筋肉量の増加というデメリットで打ち消される、と捉えていただければ問題ありません。
では一体どのようなトレーニングを行えば、効率的に持久系スポーツのパフォーマンスを高めることができるのでしょうか?
その答えはズバリ「高重量・低回数」のトレーニングになるのですが、わかりやすく順を追って説明したく、ここに「A」と「B」がいると仮定します。
2人は身長・体重・年齢・性別・筋肉量等何から何まで同じで、異なる点はただ1つ「筋の性能」であり A は筋持久力に優れ B は筋力に優れている、です。
筋力とは文字通り筋肉の発揮できる能力のことですが、1回で持ち上げることの出来る最大重量によって筋力は計られます(最大筋力)。
厚生労働省 健康日本21アクション支援システムより引用
A は大きな力を出せないけど疲れにくく B は大きな力を出せるけど疲れやすい、こんなイメージになります。
スクワットの最大挙上重量を、かなり極端ですが
A:100kg
B:200kg
と仮におき、60%1RMの重量で最高何回反復できるか? に挑戦したとすると、当然 A の勝利かと思われますが、この勝負で扱われた負荷は相対的には等しく設定されているものの、絶対的な数値では倍の差が存在します(Aは60kg Bは120kg)。
今度は扱う負荷を相対的ではなく絶対的に等しく設定し、60kgの重量で最高何回反復できるか? に挑戦したとすると、結果はおそらく B の勝利で終わるはずです。
60kgは A にとって60%1RM = MAXの60%の重量なのに対し B にとってはわずか30%1RM = MAXの30%の重量に過ぎません。
つまり、
「筋持久力それ自体は A の方が優秀であり、負荷を相対的に等しく設定したケースでは最高反復回数で A が勝つ。しかし、筋力は B の方が優秀であり、負荷を絶対的に等しく設定したケースでは最高反復回数で B が勝つ可能性があると推測される。なぜなら、反復1回あたりの “負担” が減るためだ」
とまとめられます。
※ 本来は自身の体重も考慮すべきですが、解説が複雑になる関係で省略しています。
勘の良い方ならすでにお気づきかもしれませんが、持久系スポーツのパフォーマンスを高めるためには、筋持久力の改善に加え筋力の増加を図るのが最善の策です。
筋力が増加すると、先ほど例に挙げた B と同様の状況が起こります。
スクワットの最大挙上重量が100kgから110kgに、110kgから120kgに変われば(すなわち筋力が増加すれば)、マラソンやトライアスロンなどの持久系スポーツにおいて同じ距離を移動するにしても、1歩あたりの “負担” が 軽減され、パフォーマンスに好影響をもたらすことになるでしょう。
では一体どのようなトレーニングを行えば、効率的に筋力を増加させることができるのかというと、それが高重量・低回数のトレーニングです。
実際、去年の2024年公開の「アンブレラレビュー」によると「低負荷(60%1RM未満、または15RM以上)と比較して、高負荷(80%1RM以上、または8RM以下)ではより大きな筋力の増加効果が期待される」と結論付けられています。
また、セット数が同等に定められていた場合、高負荷のトレーニングは中負荷のトレーニングと比べ、筋肉量の増加は劣っていながらも筋力の増加は秀でていました。参考:筋トレに高重量は必要ない? 筋力を向上させるには重い重さが効果的
よって、高重量・低回数でのトレーニングは、筋肉量(体重)の増加を最小限に & 筋力の増加を最大限に狙える戦略だと言えます。
持久系スポーツのパフォーマンスを高めるトレーニングとして高重量・低回数をオススメしているわけですが、果たしてこれが本当にそうなのかは疑問が残ることでしょう。
この問いに返答しているのが例えば下の研究で、
Maximal strength training improves running economy in distance runners
よく訓練されたランナーを対象に、週3回の頻度で8週間に渡り高負荷(4RM・4reps)でのスクワットトレーニングを実施したところ、
・コントロールグループ(トレーニングを実施しないグループ):測定項目に有意な改善は認められなかった。
・介入グループ(トレーニングを実施するグループ):ランニングエコノミーは「+ 5.0%」最大有酸素性走速度での疲労困憊までの時間は「+ 21.3%」で有意な改善が認められた。体重は変化しなかった。
との結果が得られました。
ランニングエコノミーとか最大有酸素性走速度での疲労困憊までの時間とか、聞き馴染みのない単語が登場しているかもしれませんが、ざっくりランニングエコノミーは「燃費」最大有酸素性走速度での疲労困憊までの時間は「ある走速度を維持できる時間」のことで、要はエネルギー効率が上がった & スピーディーに長く走り続けられるようになった、という意味です。
そして、去年の2024年公開の「システマティックレビュー & メタアナリシス」によると「低負荷 〜 中負荷(40 〜 79%1RM)と比較して、高負荷(80%1RM以上)ではより大きなランニングエコノミーの改善効果が期待される」と結論付けられています。
個人的な経験論を孕みますが、状況によっては低重量・高回数のトレーニングでも、持久系スポーツのパフォーマンスを高めることはできると感じます。
しかしながら二部作で綴ってきた通り、持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングでオススメなのはやはり、高重量・低回数です。
前作でも記載したように、競技力向上を目的としたトレーニングは「当該スポーツでは手に入れることが難しい適応 = 身体能力を安全かつ効果的に手に入れること」が本質になります。
持久系スポーツのパフォーマンスを高める = 低重量・高回数のトレーニングとは必ずしも成り立たないことを理解し、ぜひ高重量・低回数のプログラムに励んでいただけると幸いです。
最後に
今回は「持久系スポーツの競技力向上を目的としたトレーニングは低負荷ではなく高負荷がオススメ ②」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?
次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か
施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。