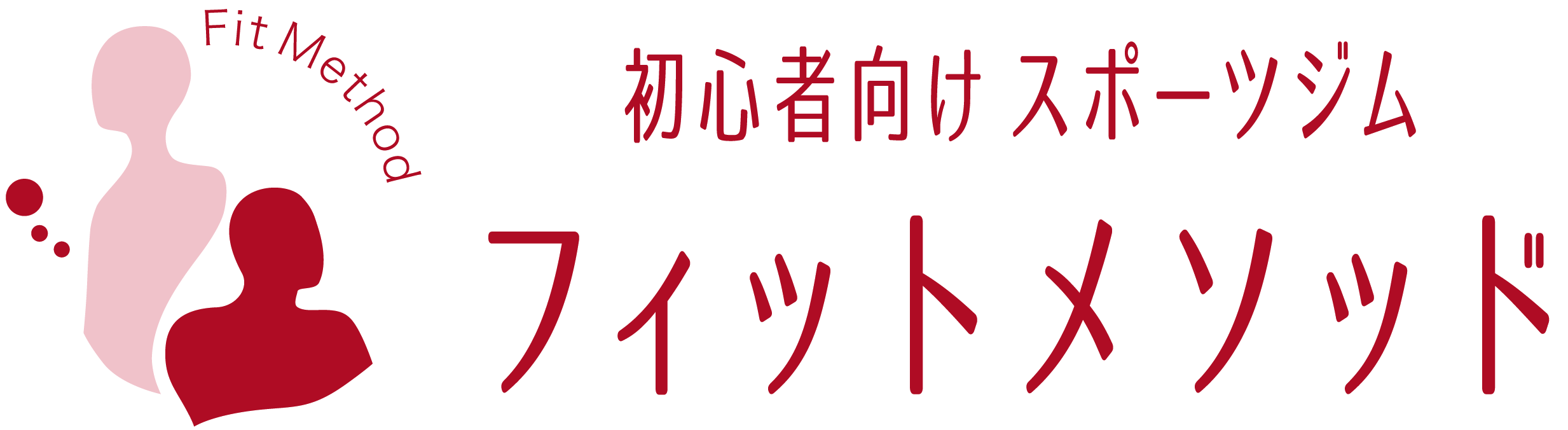札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。
「絶対に」というわけではないのですが、トレーニングにおける筋肉量の増加効果は、動作の範囲 = 関節可動域によって異なるとの報告がなされており、基本的には筋長が長い、言い換えると「その筋によりストレッチが生じるポジション」で負荷を掛けることで大きくなると考えられています。
例えば (1) では、成人女性を対象に異なる関節可動域でカーフレイズを実施し、ふくらはぎの筋である腓腹筋にどのような影響が及ぶのかについてを調べました。
詳しくは「筋トレでは “筋肉を伸ばす” “ストレッチをかける” を意識することが大切」⇦ をご覧いただきたいのですが、腓腹筋が「伸びた状態で負荷を掛けるパターン」と「縮んだ状態で負荷を掛けるパターン」では、前者の方でより大きな肥大が確認されたとのことです。
これと似たようなデータはいくつか存在しており、筋肉量の増加を目的にトレーニングを行う場合は、ストレッチ系のエクササイズをメニューに組み込むことが今現在推奨されています。
しかしながら、ここにもう1パターンを加えて、筋が「伸びた状態で負荷を掛けるパターン」と「縮んだ状態で負荷を掛けるパターン」と「伸びた状態で & 縮んだ状態で交互に負荷を掛けるパターン」があったとしたら、筋肉量の増加効果にはどのような影響が及ぶのでしょう。
今回は「動作の範囲 = 関節可動域とその組み合わせがトレーニングの効果に及ぼす影響」というタイトルで記事を書いていきます。
4つの異なる関節可動域が筋肉量の増加や筋力の向上に及ぼす影響について
From full to partials: Investigating the impact of range of motion training on maximum isometric action, and muscle hypertrophy in young women
研究内容をザックリ書き出します。
過去半年間に渡ってトレーニング経験がない女性を対象に「初期可動域」「後期可動域」「交互可動域」「全可動域」のいずれかに振り分け、レッグエクステンションを週3回の頻度で12週間実施した。
研究の前後で、大腿四頭筋の断面積、および膝関節屈曲100°・65°・30°における最大随意等尺性筋力を測定した。
= 結果 =
・大腿四頭筋の断面積は「初期可動域」「交互可動域」「全可動域」が同様に増加し「後期可動域」よりも大きかった。
・膝100°の最大随意等尺性筋力は「初期可動域」と「交互可動域」で最も増加した。
・膝65°の最大随意等尺性筋力は、全ての可動域で同様に増加した。
・膝30°の最大随意等尺性筋力は「後期可動域」と「交互可動域」で最も増加した。
この研究では、過去半年間に渡ってトレーニング経験がない女性を対象に「初期可動域」「後期可動域」「交互可動域」「全可動域」のいずれかに振り分け、レッグエクステンションを週3回の頻度で12週間実施し、大腿四頭筋の断面積、および膝関節屈曲100°・65°・30°における最大随意等尺性筋力の変化についてを調べています。
7日ごとに1回適正かどうか負荷の調整が行われ、60%1RM・7回・3 〜 6セットをプログラムとしたようです。
各可動域ですが、これは膝関節を動かす範囲が下記のように定められており、
| 初期可動域 | 100° 〜 65° |
| 後期可動域 | 65° 〜 30° |
| 交互可動域 | 100° 〜 65° と 65° 〜 30° を1回のセッションごとで変える |
| 全可動域 | 100° 〜 30° |

初期可動域は「下半分」後期可動域は「上半分」交互可動域は「下半分と上半分をローテション」全可動域は「下から上まで全部」だと捉えていただければ大きな問題はないでしょう。
そして結果ですが、まず大腿四頭筋の断面積は、
「初期可動域」「交互可動域」「全可動域」が同様に増加し「後期可動域」よりも大きかった。
となりました。
見方を変えると、初期可動域を伴ったパターンで大きな筋肥大が見られたと言えます。
冒頭で触れた通り、トレーニングにおける筋肉量の増加効果は、基本的には筋長が長い、言い換えると「その筋によりストレッチが生じるポジション」で負荷を掛けることで大きくなると考えられているため、まさにそれが現れた感じです。
次、膝関節屈曲100°・65°・30°における最大随意等尺性筋力 (ググッと強い力を発揮する能力) ですが、
膝100°の最大随意等尺性筋力は「初期可動域」と「交互可動域」で最も増加した。
膝65°の最大随意等尺性筋力は、全ての可動域で同様に増加した。
膝30°の最大随意等尺性筋力は「後期可動域」と「交互可動域」で最も増加した。
となりました。
これは「関節角度特異性」などと呼ばれており、トレーニングで得られる筋力の向上効果は「負荷が掛かった関節の角度周辺で顕著に現れる」という現象で、つまり膝を曲げたところでの力をつけたいのであれば膝を曲げたところでのトレーニングが、膝を伸ばしたところでの力をつけたいのであれば膝を伸ばしたところでのトレーニングが推奨されています。
主要だと思われる部分だけを抜粋しましたが、筋肉量の増加や筋力の向上を目的にトレーニングを行う際、少なくともレッグエクステンションを用いる場合は「交互可動域」が最も効果的みたいです。
制限された関節可動域でのトレーニングは扱う重量を増加させ、ときには怪我のリスク上昇に繋がる危険性が考えられるため、当ジムでは原則として王道の「全可動域」を取るよう指導にあたっています。
が、もし効果をさらに高めたいのであれば、タイミングを見計らって「交互可動域」をメニューに組み込むのもアリでしょう。
研究数が少ないため、他の部位にもこの結果を応用可能とは断言できませんが、やる価値は十分にあるかと思います。
最後に
今回は「動作の範囲 = 関節可動域とその組み合わせがトレーニングの効果に及ぼす影響」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?
次回作もご期待ください。
参考文献
(1) Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial Range of Motion Training Performed at Long Muscle Lengths

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か
施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。