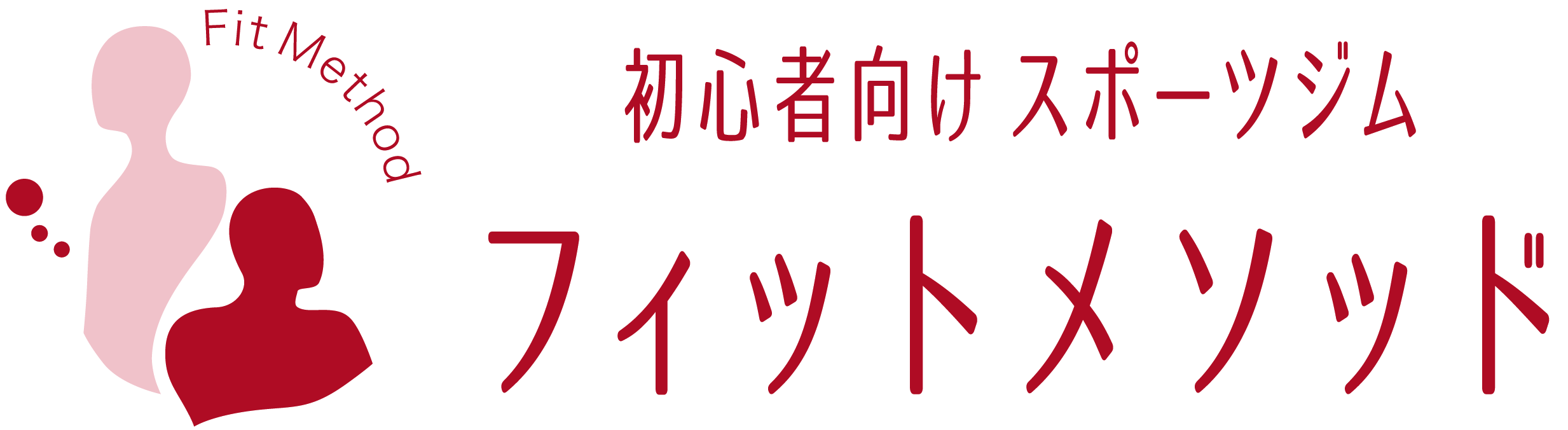札幌市中央区東本願寺前駅にある、初心者向けスポーツジム フィットメソッドです。
先日 X にて非常に共感できるポストを目にしました。
「寝たら体が回復する」と思っている人は多い。だが、元オリンピック代表コーチに教わったこの言葉を知ってから、考え方が変わった。「動の疲れは静で取る。静の疲れは動で取る。」体を酷使した日には休むことが必要だが、デスクワークでじっとしている日こそ本当は「動くこと」が必要になる。…
— 三宅裕之|Miyake Hiroyuki (@hiroyuki_miyake) October 6, 2025
私も以前、先輩パーソナルトレーナーよりほぼ同じセリフを聞いており、妙に納得した記憶があります。
この思考はシンプルながらも奥が深く、おそらく皆様の生活を有意義なものへと昇華させることでしょう。
今回は「静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る。日常をより豊かにするためのヒント」というタイトルで記事を書いていきます。
静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る。
まず、私たちが受ける疲労は「静的なもの」と「動的なもの」の大きく2つに分類することができる、と考えるところからスタートです。
窮屈な車内で何㎞も移動するとか、長時間同じ姿勢でパソコンと向き合うとかによって生じた疲れは静的な疲労、マラソンに挑戦するとか、重い荷物をマンションの最上階まで階段を使って運ぶとかによって生じた疲れは動的な疲労に区別されます。
なお、嫌いな顧客に対してのクレーム処理だったり、頭をフル回転させる試験だったり、精神的あるいは認知的な疲れは静の疲労に当てはまり、要はシンプルに身体を酷使した疲労が動だと捉えていただければ問題ありません。
静の疲労も動の疲労も同じ「疲れ」ではあるものの、種類と言いますか「質」は異なり、結果リカバリーの方法も変わる、というのが「静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る」の肝です。
例えば窮屈な車内で何㎞も移動したり、嫌いな顧客に対してのクレーム処理など静の疲労に関しては、ラジオ体操やトレーニングなど身体をほぐし鍛える「動」の実施が、例えばマラソンに挑戦したり、重い荷物をマンションの最上階まで階段を使って運ぶなど動の疲労に関しては、リラクゼーション系のストレッチや睡眠など身体を休める「静」の実施が具体的なアプローチとして挙げられます。
では果たして本当に「静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る」が日常をより豊かにするためのヒントになるのかというと、個人的には大いになり得る印象です。
身近な病気として「うつ病」がありますが、原因の1つには心理的なストレス(静の疲労)が考えられており、しかしトレーニング(動)を行うことによって、その症状は有意に改善する可能性が示唆されています。
また、トレーニングもやればやるだけ(動の疲労)効果的というわけではなく、むしろセット数を少なくした方が筋肥大や筋力向上が認められたとの報告もなされており、これは見方を変えると休息(静)の重要性を説いているとも判断できるでしょう。
Effects of a Modified German Volume Training Program on Muscular Hypertrophy and Strength
もっとも、必ずしも「静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る」が最適なのかと問われるとそうでもなく、状況によっては静の疲労を静で取る方が良いシーンもあるかと思いますし、逆も然りです。
ただ、先ほど科学的な知見を一部紹介した通り、大抵の場合この思考で悪いことはほぼ起こりません。
疲労のタイプを見極め、そして適切なリカバリーを実践する癖を身につけてもらえると幸いです。
最後に
今回は「静の疲労は動で取り、動の疲労は静で取る。日常をより豊かにするためのヒント」というタイトルで記事を書いてきましたがいかがだったでしょうか?
次回作もご期待ください。

札幌市近郊にお住いの方は、新しいカタチ ビギナー特化の フィットメソッド か
施設占有 完全マンツーマンのパーソナルトレーニングジム スタイルメソッド をご利用ください。